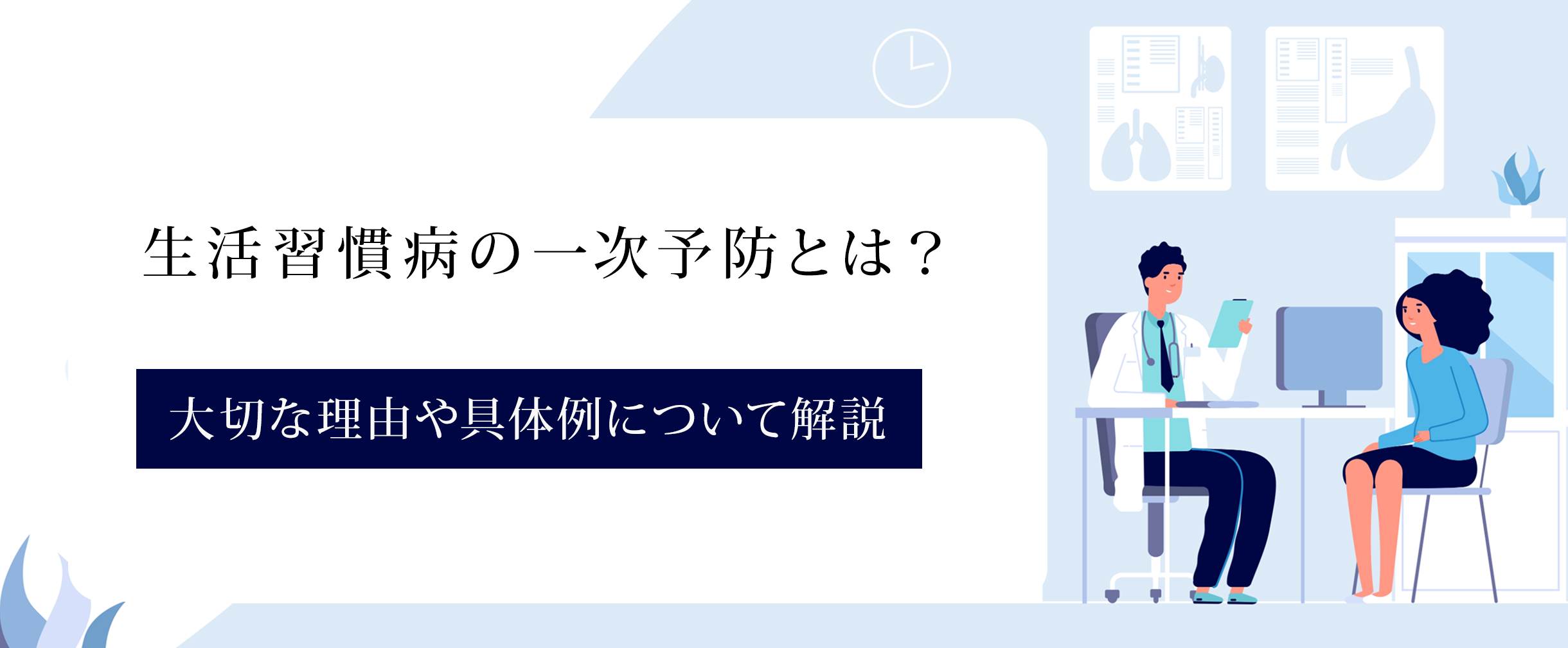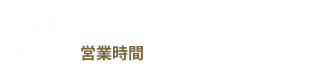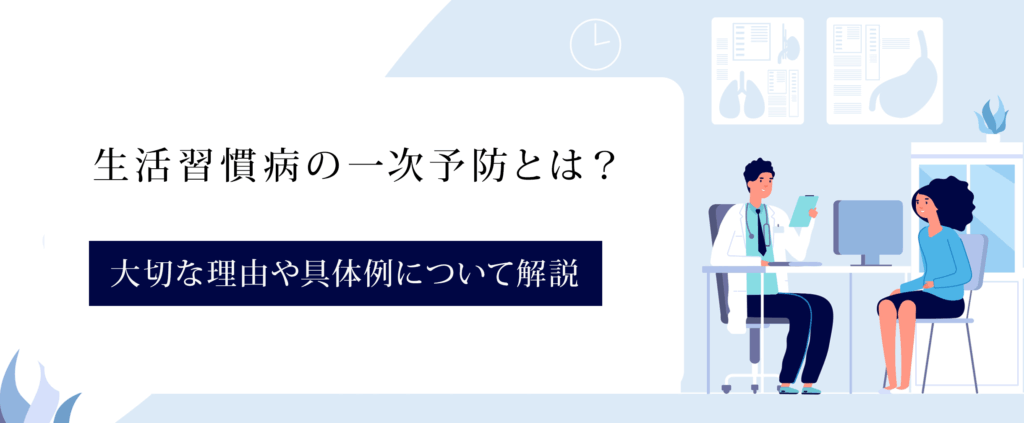


糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病は知らず知らずのうちに進行し、ある日突然、仕事や人生に大きな影響を及ぼします。多忙な経営者にとって、健康は何よりの資産。生活習慣病で体調を崩してしまうと、事業にも深刻なダメージをもたらしかねません。だからこそ、病気の発症そのものを防ぐための「一次予防」が重要になってきます。本記事では、生活習慣病の一次予防の意味や必要性のほか、一次予防の具体的なポイントなどについて解説いたします。
この記事の監修者
吉岡 悠里可
管理栄養士・日本抗加齢指導士・NRサプリメントアドバイザー
所属/日本抗加齢医学会・日本病態栄養学会・日本臨床栄養学会
予防医療とは
生活習慣病を予防することは、健康管理の根幹です。予防医療とは、生活習慣病などの病気の発症を未然に防ぎ、健康を維持・促進することを目指す医療分野のことです。近年は、従来の治療中心の医療ではなく、病気になる前にリスクを減らす予防医療にウェイトが置かれるようになっています。特に、高齢化が進む日本では健康寿命の延伸が課題であり、そのためには生活習慣病の予防が鍵になるとされています。
生活習慣病とは?主な種類と原因
生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、発症・進行に関与する疾患群」のことです。かつては「成人病」と呼ばれていましたが、生活習慣の改善によって予防が可能であるという認識から、現在の「生活習慣病」という呼称が定着していきました。
生活習慣病の範囲に明確な定義はありませんが、健康増進法では「がん及び循環器病」、健康日本21(第三次)では「がん、循環器病、糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)等」が生活習慣病と位置付けられています。厚生労働省のe-ヘルスネットでは、生活習慣病には「がん(悪性新生物)、心疾患(狭心症や心筋梗塞などの心臓病)、脳血管疾患(脳梗塞やくも膜下出血などの脳の病)などの病気が含まれる」と説明しています。
こうした病気の主な原因は、塩分の過剰摂取、脂質の多い食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスといった日々の生活習慣にあります。たとえば、運動不足は肥満や高血圧を招き、糖尿病のリスクを高めることが明らかになっています。
一次予防とは?

一次予防とは、病気の発症自体を未然に防ぐための活動です。生活習慣病などの疾病リスクを根本から低減させる、いわば「病気の原因をつくらない」ための取り組みだと言えるでしょう。
一次予防の具体的なアプローチは、バランスの取れた食事、定期的な運動、禁煙といった生活習慣の改善が中心になります。病気の兆候がない段階から健康的な生活を心がけ、将来の疾病リスクを最小限に抑えることが一次予防の大きな目的です。
これに対し、後述する二次予防は、健康診断やがん検診、人間ドックなどを受診することで病気を早期発見し、早期治療につなげる取り組みのことを言います。また、三次予防は、発症した病気の再発防止や機能回復を目指す取り組みのことです。
▼関連リンク
図 4 生活習慣病予防及び介護予防の「予防」の段階|厚生労働省
二次予防とは?
二次予防とは、自覚症状がない段階で病気を早期発見し、早期治療へとつなげるための取り組みです。特に、生活習慣病は初期段階での自覚症状に乏しいため、二次予防の役割は極めて重要になります。
二次予防の具体的なアプローチとしては、健康診断や人間ドック、がん検診などの定期的な受診が挙げられます。こうした検査・検診によって病気を早期に発見できれば、治療の選択肢が広がり、身体的にも経済的にも少ない負担で健康の回復を目指すことができます。
三次予防とは?
三次予防とは、すでに発症してしまった病気の進行抑制、再発防止、そして残された機能の維持・回復を目指す取り組みです。治療後の社会復帰を支援し、生活の質(QOL)を高めることが三次予防の主な目的です。
三次予防の具体的なアプローチとしては、脳卒中後のリハビリテーション、心筋梗塞後の心臓リハビリ、糖尿病患者に対する継続的な食事療法や運動療法、薬物療法などが挙げられます。病気と付き合いながらも、自分らしい生活を送るための重要な取り組みだと言えるでしょう。とで、より高いアンチエイジング効果が期待できます。
一次予防が重視される理由

昨今、一次予防が重視されているのは、個人の健康寿命を延伸し、社会全体の医療費を抑制するうえで、一次予防がもっとも費用対効果の高いアプローチだからです。病気が発症してからの取り組みである二次予防や三次予防に比べると、健康なうちから生活習慣を改善し、病気の発症リスクそのものを低減させる一次予防は心身の負担が少なく、生活の質(QOL)の維持に直結する取り組みだと言えます。
特に、多忙な経営者は生活習慣が乱れがちで、生活習慣病のリスクも高くなります。自身の健康悪化によって事業に影響が及ぶのを避けるためにも、一次予防が欠かせません。一次予防に力を入れることが、自分の未来を守り、会社の損失を防ぐことにつながるのです。
生活習慣病の一次予防の方法
生活習慣病にならないよう、今日からできる一次予防として「食事」「睡眠」「運動」のポイントをお伝えします。
バランスの良い食事
生活習慣病の一次予防の根幹をなすのが、バランスの良い食事です。バランスの良い食事は、エネルギー源となる主食(ご飯、パンなど)、身体をつくる主菜(肉、魚、大豆製品など)、身体の調子を整える副菜(野菜、きのこなど)を揃えるのが基本です。
特に、現代人に不足しがちな野菜の摂取は重要です。野菜には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、私たちの健康の保持・増進に欠かせない食品です。野菜を十分に摂取することで、心血管疾患や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の予防が期待できます。そのため、国は「健康日本21(第二次)」で1日350g以上の野菜摂取を推奨しています。
塩分の過剰摂取は高血圧の原因になるため、注意が必要です。「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、成人男性で1日に7.5g未満、成人女性で1日に6.5g未満の摂取が目標量とされています。脂質の過剰摂取も肥満や脂質異常症につながるため、揚げ物を避け、蒸し料理を選ぶなど、調理法を工夫することも大切です。
食事は1日3食を基本とし、規則正しく摂ることが重要です。朝食を抜くことや夜遅くに食事を摂ることは、できるだけ避けましょう。また、お酒は「適量」を意識することが大切です。適量の目安は、純アルコールで1日20gとされています。これは、ビールならロング缶1本(500ml)、焼酎なら約90ml、ウイスキーなら約60mlに相当します。
十分な睡眠
生活習慣病の一次予防では、十分な睡眠も重要な柱になります。睡眠は、心身の疲労回復、免疫機能の維持、記憶の定着など、私たちが心身ともに健康に生きていくうえで非常に重要な役割を担っています。睡眠不足が続くと、高血圧や糖尿病、肥満など、生活習慣病のリスクが高まることは様々な研究によって明らかになっています。
睡眠は、「量」と「質」の両方を意識することが大切です。睡眠の量は、文字どおり睡眠時間です。睡眠の質は、睡眠休養感(朝、目覚めたときに感じる休まった感覚)だとされています。良い睡眠をとるためには、睡眠の量と質が十分に確保されていることが重要です。
睡眠の質を高めるため、日頃から以下のポイントを意識するようにしましょう。
- 規則正しい生活習慣を身につける
- 寝室環境を最適化する
- ストレス解消に努める
- 食事・入浴の時間に配慮する
- 運動習慣を身につける
睡眠の質を高めるポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
▼関連リンク
睡眠の質を上げる方法は?質が下がる原因も紹介
※「睡眠の質を上げる」の記事へリンク
適度な運動
生活習慣病の一次予防において欠かせないのが、適度な運動です。適度な運動は、血圧や血糖値の安定、中性脂肪の減少など、様々な健康効果が期待できます。逆に運動不足は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などのリスクを高めます。
一次予防としての運動は、必ずしも激しいトレーニングをする必要はありません。厚生労働省は、今より10分多く身体を動かす「+10(プラステン)」を推奨しています。、+10によって、「死亡リスクを2.8%」「生活習慣病発症を3.6%」「がん発症を3.2%」「ロコモ・認知症の発症を8.8%」低下させることが可能であることが示唆されています。
忙しい日常生活の中でも、少しだけ意識して身体活動量を増やしてみましょう。たとえば、エレベーターを使わずに階段を使う、一駅手前で降りて歩く、目的地まで遠回りして歩くといった工夫が考えられます。毎日の生活習慣に取り入れやすい運動を見つけ、継続することが生活習慣病の予防につながります。
セルフチェック項目
以下は、カリフォルニア大学のブレスロー教授が提唱した「7つの健康習慣」です。当てはまる項目が多いほど、生活習慣病のリスクは低いとされています。
□ 喫煙をしない
□ 定期的に運動をしている
□ 飲酒は適量を守っている(または飲酒しない)
□ 1日7~8時間の睡眠をとっている
□ 適正体重を維持している
□ 毎日朝食を食べている
□ 不要な間食をしない
二次予防、三次予防が必要になるケースについて
一次予防として生活習慣の改善に努めていても、加齢や遺伝的要因など、すべてのリスクを排除することはできません。そこで、必要になるのが二次予防です。定期的に健康診断や人間ドックを受診していれば、万が一病気が潜んでいても早期発見・早期治療が可能になります。
三次予防は、生活習慣病が発症してしまったときに必要になります。病気の重篤化や再発を防ぎ、生活の質(QOL)を維持していくうえでは、三次予防が重要な役割を果たします。
まとめ
生活習慣病は、「そもそも発症させないこと」を目指す一次予防が極めて重要です。ただし、生活習慣病のリスクは人によって異なるため、一律の対策では不十分な場合もあります。だからこそ、人間ドックなどの二次予防にも力を入れる必要があります。SBIメディックの人間ドックでは、一般的な健康診断では受けられない高精度な生活習慣病検査を実施しています。経営者など、社会的な責任を担う立場にある方は、ご自身だけでなく、ご家族や職場、社会のためにも、生活習慣病の予防、早期発見に努めていただきたいと思います。
SBIメディックでは、東京駅直結の上質な空間で会員制人間ドックを受けることができ、経営者をはじめとするエグゼクティブの方々に向けた国内最高峰の予防医療サービスをご提供しています。人間ドックを中心とする「予防サポート」はもちろん、専門医のご紹介やセカンドオピニオンなどの「治療サポート」、抗加齢医療や再生医療、エイジングケア、デンタルケアなど加齢に伴い重要になる「エイジマネジメント」までを一体でご提供することで、「いつまでも若々しく健やかな人生」をお送りいただけるようサポートいたします。
▼関連リンク
会員制人間ドック「SBIメディック」の詳細はこちら
※参考:
生活習慣病とは? | e-ヘルスネット(厚生労働省
アクティブガイド | e-ヘルスネット(厚生労働省)
健康日本21(第二次) |厚生労働省
「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書|厚生労働省