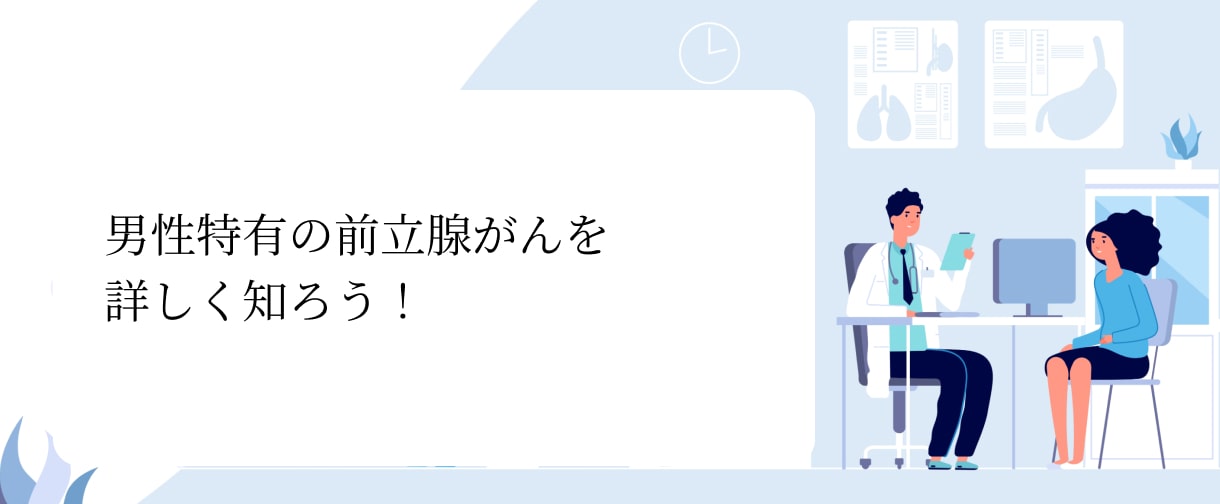前立腺がんは、血尿で判明する膀胱がんと異なり、初期段階での自覚症状や痛みがないため、無症状のまま転移する恐れがあります。悪性腫瘍(がん)は早期発見・早期治療が叫ばれて久しい状態ですが、「前立腺がん」は多くの場合比較的ゆっくり進行することで、 早期に発見し適切な治療を行えば治癒が望めます。
前立腺がんの概要
前立腺は、男性のみにある臓器で膀胱の下にあり、尿道をとり囲むように位置しています。前立腺は精液の一部である前立腺液を作っており、精子に栄養を与えたり、運動能力を高めたりする働きを持っています。前立腺液はPSA※1というたんぱく質を含んでいます。
※1:PSAとは前立腺特異抗原の略語で、前立腺疾患(前立腺がん、前立腺肥大症、前立腺炎のみ)でしか上昇しないマーカーです。
前立腺がんは、血尿で判明する膀胱がんと異なり、初期段階の自覚症状や痛みはほぼありません。無症状のまま転移することもあり、骨に転移した場合には激しい痛みが現れることがあります。がんができやすいのは前立腺の辺縁域と呼ばれる領域です。
前立腺がんの診断は、血液検査におけるPSA値を根拠として「前立腺がん疑い」となれば、前立腺肥大や炎症などと鑑別するため再度PSAを測り、さらにMRI検査や超音波検査、直腸診などを行い異常所見の有無を確認します。このような検査を経て、がんが疑われれば前立腺の細胞を採取して直接顕微鏡で調べる「前立腺生検」を行います。この生体検査については、12か所以上採取することが推奨されています。
採取した細胞を顕微鏡で見ると、がんには「顔つき」があるとよく言われます。転移しそうな悪い顔つきのがん細胞もあります。面積ごとに5段階評価をして採点し、合計6点未満であれば、何も治療せず経過観察となります。「今回は治療をしませんが、3か月ごとにPSA検査をしてください」という結果になり、時間経過と共にPSAが上昇するようであれば再度、生検を行い悪い細胞に変化していないかを確認する必要があります。

前立腺がんの病期の分類方法
前立腺がんの治療方針は、がんの「進行の程度(病期)」と「悪性の程度(悪性度)」によって分類されます。
◇TNM分類
前立腺がんの病期(がんの進行度)を分類する方法の一つに「TNM分類」があります。これは、がんの大きさや広がりを評価するための国際的な基準で、TNM分類は3つの要素から成り立っています。
まず、「T」は腫瘍(Tumor)の広がりを示します。T1からT4までのステージがあり、数字が大きくなるほど腫瘍が大きくなり、前立腺の外に広がっていることを意味します。例えばT1は腫瘍が小さく、前立腺の中にとどまっている状態です。
次に「N」はリンパ節(Nodes)への転移を示します。N0はリンパ節にがんが広がっていないことを示し、N1はがんが近くのリンパ節に転移していることを意味します。
最後に「M」は遠隔転移(Metastasis)を示します。M0は遠くの臓器や組織にがんが広がっていないことを意味し、M1はがんが他の臓器や遠くの部位に転移していることを示します。
◇組織学的分類(グリソンスコア)
組織の病理検査でがんと診断された場合、その悪性度を分類します。がん細胞の増殖、転移、再発の程度を表した「グリソンスコア」は前立腺がんの判定に広く使用されています。2から10までの9段階で評価され、数字が大きいほど悪性度が高いことを表します。
グリソンスコア6以下・・・比較的進行が遅い高分化型前立腺がん
グリソンスコア7・・・・・中等度の悪性度の前立腺がん
グリソンスコア8以上・・・悪性度の高い低分子の前立腺がん
◇リスク分類
転移のない前立腺がんは、再発のリスクを考慮しながら「リスク分類」を用いて治療方針を決めていきます。
前立腺がんのリスク分類は複数ありますが、多くの場合、がんの進行具合や再発の可能性を「低リスク」、「中リスク」、「高リスク」の3つに分類し、治療方法の選択に役立てます。
・低リスク:がんが前立腺内にとどまっており、PSA値が10以下、かつグリソンスコア(がんの悪性度を示す数値)が6以下の場合。この場合、がんはゆっくり進行し、治療の選択肢には経過観察や軽度の治療があります。
・中リスク:PSA値が10から20の間、またはグリソンスコアが7の場合。がんが前立腺内にあるが、進行する可能性があるため、手術や放射線治療が検討されます。
・高リスク:PSA値が20以上、またはグリソンスコアが8から10の場合。がんが前立腺の外に広がるリスクが高く、より積極的な治療(手術、放射線治療、ホルモン療法など)が必要です。
医師は、TNM分類、グリソンスコア、PSA値などをもとにリスク分類を行い、治療方針を決めていきます。
前立腺がん治療の選択方法
前立腺がん治療の選択は、がんの進行度や身体の状態、生活スタイルなどを考慮して行われます。主な治療法には、手術、放射線治療、ホルモン療法、化学療法などがあります。
治療は、前立腺だけに留まる「前立腺限局がん」であることをまず確認する必要があります。前立腺がんの転移は相性の良い場所があり、骨盤内のリンパ節、骨、肺の順に転移しやすいと言われています。進行がんになると肝臓や脳への転移も見られます。骨への転移では「骨シンチグラム」という検査を行う必要があります。これはラジオアイソトープを使用し総合病院でなければできません。それらの検査で転移がないと確認されれば「限定性前立腺がん」の診断が確定します
「手術」は前立腺を取り除く方法で、がんが前立腺内に限局している場合に選択されます。手術後は、尿漏れや性機能障害のリスクがありますが、
内服治療やプロスタグランジン陰茎自己注射などで数か月から年単位で改善することもあります。
「放射線治療」はがん細胞を放射線で破壊する治療法で、手術が難しい場合や再発予防のために行われます。しかし放射線は周囲の組織にも影響を及ぼす可能性があり、突然血尿や血便が出現することもあるため、抗凝固療法をしている場合は注意が必要です。。
「ホルモン療法」はがん細胞の成長を抑えるために男性ホルモンの働きを抑制する治療法です。性欲の低下や乳房の腫れ、hot flashというほてりなどの副作用が出ることがあります。まれに肝機能障害や間質性肺炎を呈することがあり注意が必要です。また長期間投与による骨粗しょう症も問題となります。
「化学療法」は全身に投与される抗がん剤を使ってがん細胞を攻撃する治療法です。しかし副作用が強いため、生殖能力や骨髄機能にも影響を及ぼす可能性があります。
治療を選ぶ際には、がんの進行度や患者の健康状態だけでなく、生殖能力への影響も考慮して慎重に決定されるべきです。治療法にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、患者様と医師がしっかりと話し合い、最適な治療法を選ぶことが大切です。
手術による治療
前立腺がんの手術治療には、前立腺全摘術があります。前立腺全摘術は前立腺と精嚢を丸ごと取り除く手術を行います。がんの状態や進行度によっては、リンパ節の摘出や前立腺周囲の性機能に関わる神経を温存(神経温存術)の選択をします。

◇前立腺全摘術
前立腺がんの手術では、前立腺を周囲の臓器ごと完全に取り除く前立腺全摘術が基本となります。がんが前立腺内に限局している場合に行われます。前立腺摘出後は、膀胱と尿道を繋ぎ直し、排尿路を確保します。
手術の方法には、開腹手術、腹腔鏡下手術、ロボット支援術などがありますが、現在ではほとんどが一番低侵襲で行えるロボット支援手術です。開腹手術や腹腔鏡下手術で行っている施設では、手術症例確保が困難で、ロボット支援手術可能な病院へ患者紹介しているのが実状です。前立腺の近くには、尿漏れや勃起に関わる神経があり、手術で神経を傷つけることがあるため、尿漏れや勃起障霜害(ED)など の合併症が起こる場合があります。この神経を残す「神経温存術」を行った場合でも、完全に合併症を予防することは困難です。
内服治療やプロスタグランジン陰茎自己注射などで数か月から年単位で改善することもあります。
◇開腹手術(恥骨後式前立腺全摘除術)
全身麻酔と硬膜下麻酔を行いながら、下腹部を切開して手術を行います。腹部を開腹して手術を行うため、ある程度の大きさの傷ができ、身体への負担が大きく、術後の痛みなどがあります。エクスパートが執刀しないと出血量が2リットルを超えることがあり、危険です。
◇腹腔鏡手術(腹腔鏡下前立腺全摘除術)
腹部に小さな穴を数か所開けて、炭酸ガスでお腹を膨らませ、専用の器具や内視鏡を挿入し手術を行います。
傷跡が小さく術後の回復が早いため、早期に社会復帰が可能ですが、ロボット手術ほど緻密に操作ができないため、合併症出現率と根治率はロボット手術よりも劣ります。
◇ロボット手術(ロボット支援前立腺全摘除術)
腹部に小さな穴を数か所開けて、精密な内視鏡や鉗子を持った手術用ロボットを遠隔操作して手術を行います。拡大画面を見ながら微細な操作ができ、出血量が少ないメリットがあります。より緻密な手術が可能なため、従来の術式よりも、術後の回復が早いことや合併症がより少ないのも利点です。
放射線療法
放射線療法は前立腺がんに放射線を照射して、がん細胞を破壊する治療法です。主な放射線療法には、体外より治療を行う組織内外部照射療法と前立腺内に放射線源を挿入する内部照射療法(密封小線源療法)があります。

◇外部照射療法
外部照射療法は体の外から放射線を照射する方法です。外部照射療法は、入院の必要がなく通院で治療を受けることができます。放射線は数分間照射され、通常は週に5回程度で、数週間から数か月治療が続きます。この治療法は、前立腺周辺の臓器にも放射線があたるため、直腸粘膜の出血や潰瘍、頻尿、排尿・排便時の痛み、勃起障害などが起こる可能性があります。重粒子線や陽子線など特殊な放射線照射治療もありますが、自己負担は高額です。
◇内部照射療法(密封小線源療法)
内部照射療法はがんの近くに放射線源を置く方法です。前立腺に放射線の小線源を永久的に埋め込み、そこから放射線を照射して周辺のがん細胞を死滅させる方法と前立腺内に針を刺し込み、その針に線源を通して放射線照射を行う方法があります。この方法はがんに対して高い放射線量を送ることができ、周囲の健康な組織に与える影響が少なくなります。放射線源はしばしば数日から数か月体内に留まり、少しずつ放射線を放出します。副作用は排尿に関するものが多いですが、徐々に低減し、外照射療法に比べ性機能が維持される割合が高い傾向にあります。しかし、再発した場合には、摘出手術は不可能です(術者の被曝リスク)。また海外渡航の際、出入国でレントゲンゲート通過許可証明書を携帯する必要があり、不携帯の場合は出入国不可です。
薬物療法
前立腺がんの薬物療法には、ホルモン療法(内分泌療法)と化学療法の2つの主要なタイプがあります。これらの治療法は、がん細胞を止めたり減少させたりするために使用されますが、その働き方や副作用が異なります。
◇ホルモン療法(内分泌療法)
ホルモン療法(内分泌療法)は前立腺がんの治療法の一つで、男性ホルモンであるテストステロンの働きを抑制することでがんの成長を抑える方法です。
前立腺がんは通常、男性ホルモンであるテストステロンに反応して成長するために、ホルモン療法ではテストステロンの生産を抑えることでがん細胞の成長を遅らせることや兵糧攻めにしてがん細胞を死滅させることが狙いです。
ホルモン療法は、以下の方法で行われます。
① 注射や錠剤によるホルモン投与:テストステロンを抑制するための薬を注射または錠剤として服用します。これにより前立腺がんの成長を抑えることや死滅が期待できます。ができます。
②手術による睾丸摘出:睾丸からテストステロンを産生する部分を取り除く手術です。これにより体内でのテストステロンの量を減らし、がんの成長を抑える効果が期待されます。
ホルモン療法の副作用としては以下のようなものがあります。
– 性欲の低下
– 勃起不全
– 体重増加
– 疲労感
・骨粗しょう症
ホルモン療法は、がんが再発したり進行している場合や手術後の補助療法として用いられることがあります。使用する抗がん剤の種類や組む合わせは個人差があり様々ですが、副作用があるため、医師がよく話し合う必要があります。生活の質を保つため、病期や年齢、身体の状態など考慮し、治療方針を決めていくことが大切です。
◇化学療法
化学療法は、がん細胞を攻撃する特別な薬(抗がん剤)を使ってがんを治療する方法です。薬によりがん細胞の増殖を妨げたり、破壊したりすることでがんを減少させる効果があります。化学療法は通常、点滴または錠剤として服用されます。ホルモン療法の効果が期待できない場合や手術ができない場合に使われることがあります。
抗がん剤は、がん細胞が分裂するときの遺伝子やタンパク質を標的にします。これによりがん細胞が増殖するのを阻止し、腫瘍の成長を遅らせたり、小さくしたりしる効果が期待できます。また副作用として、食欲低下、吐き気や嘔吐、脱毛、免疫力の低下などがあります。これらの副作用は、がん細胞だけではなく健康な細胞にも影響を及ぼすことがあります。
まとめ
前立腺がんは、男性特有の生殖器である前立腺に発生するがんで主に中高年の男性に見られ、年齢を重ねるほど発生リスクが増加傾向にあります。前立腺がんは、日本だけなく世界的にみても罹患数の多い疾病です。日本人においては、男性が罹患する最も多いがんとされています。※2
初期段階では症状がないことが多く、進行すると尿の出が悪くなったり、血尿が出たりすることがあります。前立腺がんと診断された場合、治療法には手術、放射線療法、化学療法、ホルモン療法などがあります。一般的に、これらの治療法は個々の症例によって適切なものが選択されます。
前立腺がんの摘出手術は必ずがんを含む全摘で、一般的には前立腺の後ろにある精嚢も一緒に摘出するため術後は射精ができにくくなります。また術後は尿失禁(尿もれ)などもありQOL(生活の質)は決して良いものではありません。そのため手術療法を選択する場合は、手術実績のある、執刀経験数が多い術者のいる施設での治療が望ましいといえます。しかし極力早期に発見すれば、無治療での経過観察も選択肢に入ってきます。そのような意味からも人間ドックを定期的に受けることは大変重要です。血液検査でがんがわかるのは「白血病」と「前立腺がん」だけです。
前立腺がんに罹患される方の3人に1人は現役世代(15~64歳)で、60歳以上の方に多くみられます。職場や家庭など、いろいろなものを背負う「責任世代」は病気のリスクも大きくなる年代です。健康的な生活習慣を心掛け、症状がなくても定期的な検診を受けるようにしましょう。
SBIメディックで実施している人間ドックでは、前立腺がんの早期発見のために血液検査によるPSA値の測定の他、骨盤内MRIによる検査が用意されているドックもあります。ご興味がございましたら資料請求よりお問い合わせください。
※2:2024.02.28更新 国立がん研究センター がん情報サービス「最新がん統計」より