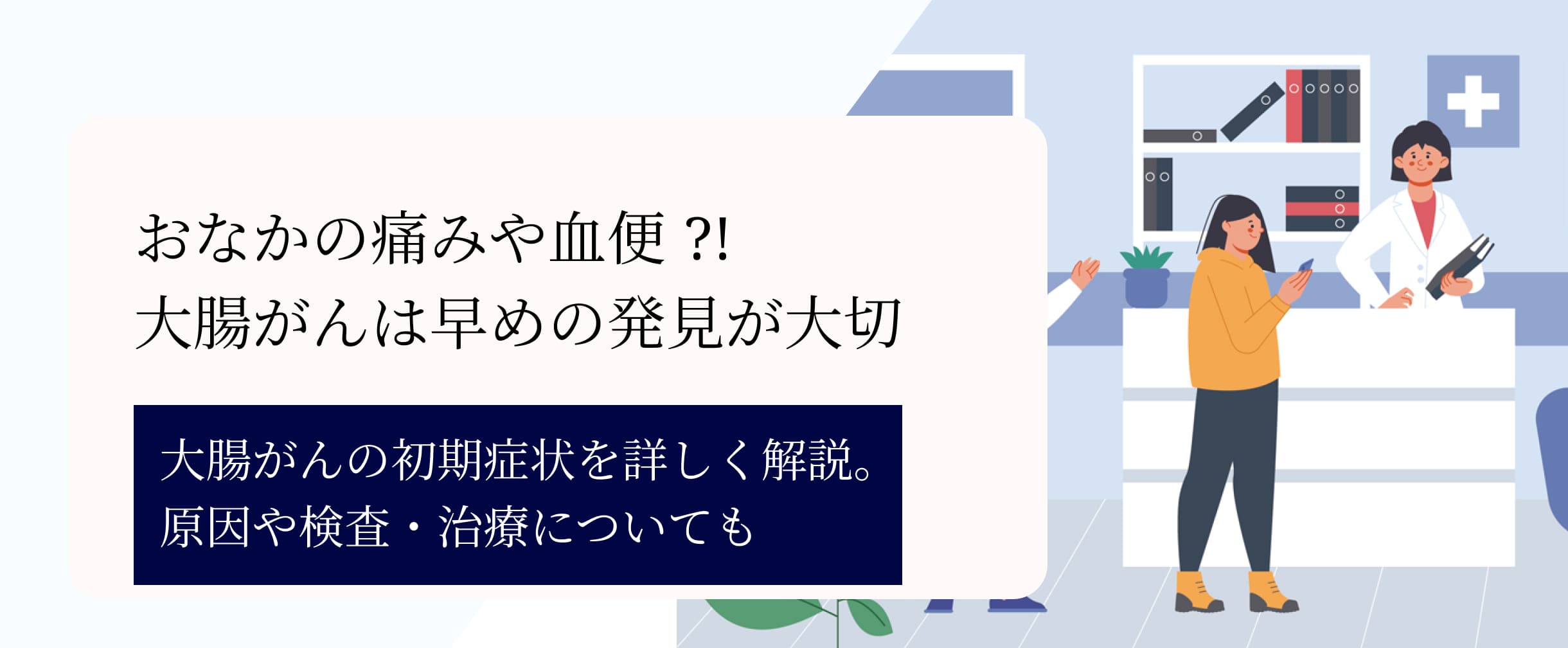大腸がんの初期症状はどのようなものか

大腸がんの初期症状には、便の性状の変化、血便や下血、体重の減少、貧血、腹痛、膨満感、残便感などがあります。これらの症状が持続する場合、油断して放置すると、大腸がんを進行させてしまう恐れがあります。
◇ 便の性状の変化
大腸がんの初期症状の一つは、便の性状の変化です。代表的な症状は、便秘や下痢、血便や下血、便の形状や色の変化などが含まれます。便の性状が通常と異なる状態が続く場合、大腸がんの可能性が考えられます。
◇ 血便がでる
血便は通常、下部消化管、すなわち大腸の出血により便の中に血液が混ざり、便が赤色に見える状態を指します。大腸がんが進行すると、がんの組織から血がにじみ出し、それが便に現れることがあります。血便が出る原因としては、がんだけでなく、大腸内のポリープ、炎症、または他の消化器系の疾患も考えられます。痔などで出血することもあるため少量の血便は放置してしまいがちですが、がんであった場合、そのままにしてしまうと進行してしまうため、わずかな出血でも即座に医師の診察が必要です。
◇ 体重が減少する
がんが大腸内で進行すると、がん細胞によって、たんぱく質や脂肪分が分解されるため、通常の摂取カロリーよりも多くのエネルギーをがんが消耗し、体重の減少がみられることがあります。また、がんによる消化器系の問題や吸収障害がある場合、栄養の吸収が困難となり、体重が減少します。食生活や生活習慣の変化がないにもかかわらず体重が減少していく場合は、大腸がん以外にも他の疾病が隠れている可能性もありますので、医療機関の受診をおすすめします。
◇ 貧血になる
がんが大腸内で進行すると、がんの存在や出血によって体内の血液量、ヘモグロビンや赤血球が減少し、これが貧血の原因となります。大腸がんによる出血は、通常は便に血が付着したり、混ざった形で現れますが、よく見ずに出血に気がつかなかったり、時には微小な出血や潜在的な出血のためわかりにくく見逃されることがあります。めまい、動悸、息切れ、立ちくらみなどの貧血の症状で来院され、大腸がんが見つかることもあります。
◇ お腹が張って痛くなる
大腸がんの初期症状の一つに、お腹が張って痛くなることがあります。がんが大腸内で進行すると、腫れや腫瘍が発生することで腸管の通り道が狭くなり、通常の便通が妨げられます。これにより、腸内の圧が上昇し、お腹が張って痛みを感じることがあります。痛みは通常、腹部の特定の場所で感じられ、時には便通と関連して増悪することがあります。放置すると腫瘍が大きくなって腸を塞ぎ、腸閉塞をひき起こします。命に関わることもありますので、放置せず、早期に医師の診断を受けることが重要です。診察では、腹部の触診や画像検査(CT、MRI)、大腸内視鏡検査などが行われ、がんの有無や進行度が確認されます。
大腸がんの初期症状に痛みはある?
大腸がんの初期症状でも以下の痛みが伴うことがあります。
1. 腹部の不快感
腹部が張り、不快感や痛みが生じます。
2. 便通に関連する痛み
腫瘍が大腸内に存在すると、通常の便通が妨げられ、腸の周りに圧がかかります。これが痛みを引き起こすことがあります。
3. 慢性的な腹痛
痛みは慢性的であり、継続的に感じられることがあります。
4. 局所的な痛み
腫瘍が特定の部位に集中している場合、その部位に局所的な痛みが生じることがあります。
5. 転移による痛み
大腸がんが進行すると、他の部位に転移し、転移した臓器によっては痛むことがあります。大腸がんによる痛みは個人によって異なり、痛みの程度や感じ方も様々です。痛みの原因や特徴は病状の進行によっても変化するため、早期の診断と治療が重要です。
大腸がんとは
大腸がんとは大腸表面の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称であり、結腸や直腸内で悪性腫瘍が発生するがんの一種です。日本で一番、罹患率が多いがんであり、死亡率では、女性1位、男性2位の疾病です。(※1)正常な組織の制御を失った細胞が異常に増殖し、腫瘍を形成します。大腸がんはポリープから進行することがあり、これががんの発生の始まりとされます。初期の段階では症状がほとんど現れず、気づきにくいため、早期発見・治療のために定期検診が何よりも重要です。
◇ 大腸の役割
大腸は消化管の末端にある臓器で、主に消化された食物の水分や電解質を吸収し、便を形成して排泄する役割を果たしています。大腸の主な役割は以下となります。
① 水分吸収
小腸での栄養素の吸収が主に終わった後、大腸では未吸収の水分や電解質が便に吸収されます。
② 便の形成
大腸での水分吸収と電解質の調整により、小腸からの未吸収物質が便として形成されます。
③ 腸内細菌の活動
大腸は豊富な腸内細菌が存在する場所であり、これらの細菌は食物の分解や発酵を行います。
④ ビタミンの生成
腸内細菌が一部のビタミンを生成します。
⑤ 便の貯蔵と排泄
大腸は最終的な便の貯蔵場所であり、適切なタイミングで排便が行われます。
大腸が健康であることは、栄養素の吸収や体内の水分調整、腸内環境の維持において大切なことなのです。
大腸がんの原因について
大腸がんの原因は複雑で、遺伝的要因や環境因子が関与しているといわれています。一般的なリスク要因には、加齢や遺伝によるもの、アルコールや喫煙、赤身肉や加工肉の摂取、大腸ポリープのがん化、肥満や運動不足などがあります。これらの要因が複合的に影響し、正常な細胞の制御を失った異常な細胞の増殖を引き起こすと考えられています。
◇ 加齢や遺伝によるもの
加齢により、細胞の分裂や修復のプロセスで蓄積した遺伝子の変異が増加し、がん発生のリスクが高まります。また、遺伝的要因も大きな影響を与えます。ご家族に大腸がんの方がいらっしゃる場合、共通の食生活や生活習慣がリスク因子となります。ご家族みんなで生活習慣を見直すことが大切です。
◇ アルコールや喫煙
アルコールは消化管において発がん性物質を生成する可能性があり、腸の細胞に悪影響を及ぼすことが示唆されています。また、アルコールの過剰摂取は栄養不足を引き起こし、これががんのリスクを高める要因となります。休肝日を設けるなど飲み過ぎに注意しましょう。喫煙においては、タバコに含まれる有害な化学物質が血液を介して大腸に到達し、細胞の損傷やがん化を促進する可能性があります。喫煙者は大腸がんのリスクが1.4倍高くなります。特に気を付けましょう。

◇ 赤身肉や加工肉の摂取
大腸がんの罹患率の増加に食の欧米化が深く関与いているといわれており、特に赤身肉や加工肉が原因といわれています。これらの食品に含まれるヘム鉄や加工の過程で高温調理する際に生成される物質に発がん性物質(ニトロソアミンなど)が、腸内で細胞の損傷やがん化を促進する可能性が指摘されています。特に、焼き肉や燻製、ソーセージ、ベーコンなどの加工肉はがんリスクの増加と関連しているとされています。魚に置き換えるなど意識しましょう。
◇ 大腸ポリープのがん化
大腸ポリープは大腸の内壁にできる小さな腫れで、一部のポリープが悪性腫瘍へ進展することがあります。特に腺腫性ポリープは『がんの前段階』と考えられ、長期間にわたって放置し大きくなるとがんに進行すると考えられています。したがって、内視鏡で発見された腺腫性ポリープは切除することをおすすめします。ポリープががんに進化するプロセスは遺伝的変異や環境要因によって影響を受けます。加えて、大腸内での炎症や損傷もがん化のリスクを増加させる要因となります。
大腸がんの検査方法
主なものでは大腸内視鏡検査があり、医師が内視鏡を使って直接大腸内を観察しポリープやがんを検出します。また、大腸CT検査は内視鏡を挿入せず、CT撮影を行い、コンピュータ処理することで大腸の画像を作成し異常を確認します。
◇ 大腸内視鏡検査(コロノスコピー)
大腸や直腸の内部を直接観察する検査です。事前に腸内をきれいにするための下剤を使用します。検査では、内視鏡を直腸から挿入し、大腸内の異常やポリープ、がんなどを視覚的に確認します。必要に応じて生検やポリープの切除も行われ、早期のがんの発見や予防が可能です。大腸内視鏡検査は大腸がんの早期発見と治療に非常に有効な手段であり、定期的なスクリーニングが推奨されています。
◇ 大腸CT検査
内視鏡を使用せずに大腸がんやポリープを見つける検査法です。肛門から細いチューブを10センチほど挿入し、コンピュータ断層撮影(CTスキャン)を用いて大腸の詳細な断層画像を取得します。検査前に腸を拡張させるため炭酸ガスを注入し、大腸を撮影します。大腸CT検査は内視鏡検査ほど侵襲的でなく、下剤も少なくすみ、大腸内視鏡検査に比べ、痛みが少なく短時間で検査することが可能です。大腸憩室やポリープ、がんを検出するのに役立ちます。
◇ 便潜血検査
大腸がんのスクリーニングに用いられる非侵襲的な検査です。便を採取し、その中に血液が含まれているかどうかを判断する検査です。便中の微量な血液を検出できるため、大腸内の異常やポリープ、大腸がんの可能性を調べることができます。便潜血陽性となった場合は放置せず、精密検査を受ける必要があります。精密検査は、大腸内視鏡検査もしくは大腸CT検査が該当します。
大腸がんの治療
大腸がんの治療は、ステージ(病期)に基づいて決まります。がんの進行度により手術、放射線療法、化学療法などを組み合わせて行います。がんが粘膜内に留まっている早期段階ではがんを切除できるかを判断し、内視鏡か手術がすすめられます。進行がんの場合、手術治療が選択され、再発を防ぐために、術前、もしくは術後に化学療法や放射線療法などが行われます。
まとめ
大腸がんの初期症状にはさまざまなものがあります。まず、便の性状の変化が一般的です。通常の便からの逸脱として、便秘や下痢、便の形状や色の異常が見られることがあります。血便も大腸がんの初期症状の一つで、便中に鮮血や暗い血液が混じることがあります。また、腹痛や腹部不快感、体重減少や貧血も初期症状として現れます。これらの症状は大腸がんの早期発見に重要な手がかりとなりますが、特定の症状がなくても大腸がんの可能性があるため、やはり定期的な検査を受けることをおすすめします。
私たちの身体では、1日5000個のがん細胞ができているといわれています。身体の中を免疫細胞がパトロールして、その都度退治してくれていますが、その監視にミスが起こると生き残ったがん細胞が増殖し塊となって、やがて悪性腫瘍になっていきます。一方で、大腸がんは早期に発見して治療すれば約90%が完治することができるといわれています。日本人の罹患率が一番多い大腸がんの早期発見のため、年に一度の大腸CT検査または、大腸内視鏡検査は最も有効です。生活習慣に気を付けつつ、検診を経年的に受けることが大切です。
※1:参考:国立研究開発法人国立がん研究センター 最新がん統計よりhttps://ganjoho.jp/reg_stat/index.html