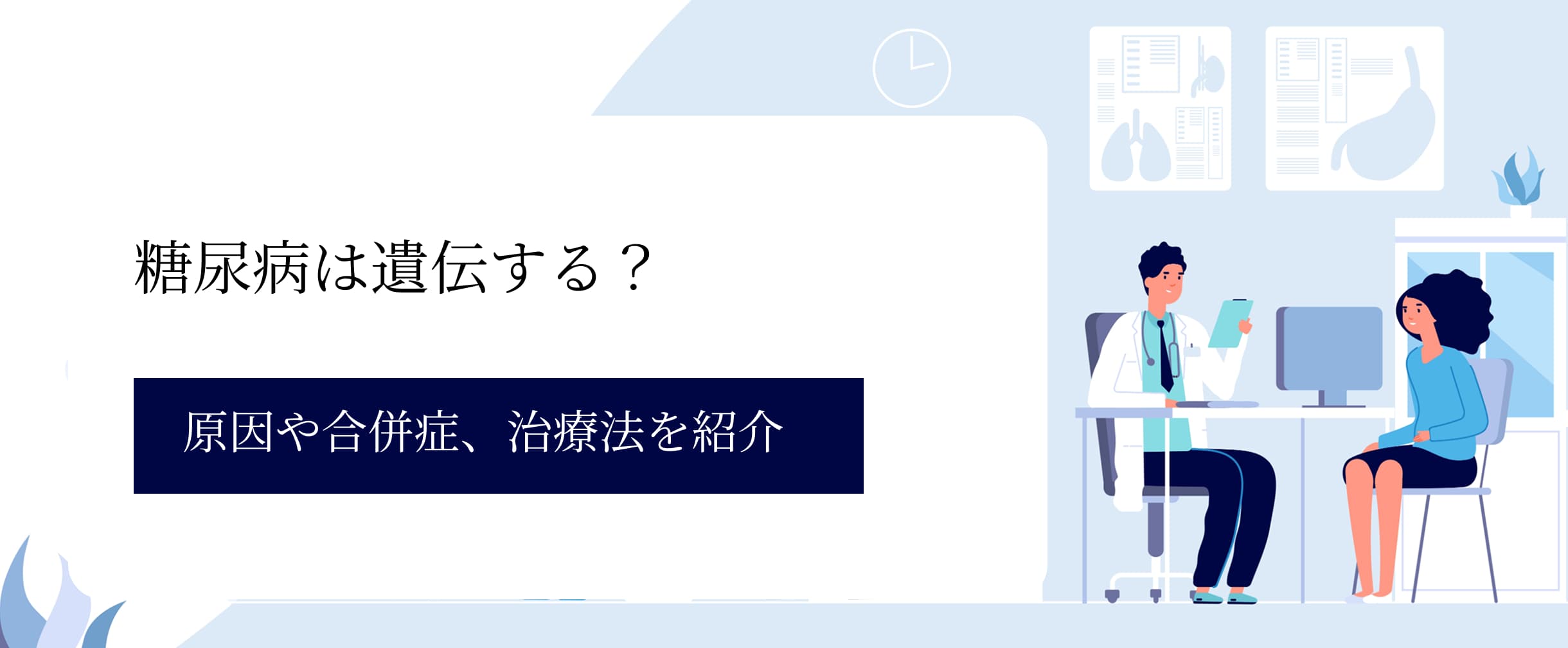日本人の糖尿病有病者と糖尿病予備群を合わせると、約2,000万人に上ると言われています。糖尿病は目や腎臓、心臓や脳血管などに合併症を起こすほか、近年ではがんや歯周病・認知症など、様々な病気と関連があることが明らかになっています。糖尿病が生活習慣病であることはよく知られていますが、遺伝的な要素も関係しているのでしょうか。今回は、「糖尿病は遺伝するのか」というテーマを中心に、糖尿病の原因や糖尿病が引き起こす可能性のある合併症、治療法などについて解説していきたいと思います。
この記事の監修者
佐藤 文彦
東京国際クリニック/糖尿病代謝内分泌科
日本糖尿病学会専門医・研修指導医、日本肥満学会専門医、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医、日本コーチ協会認定メディカルコーチ。1998年、順天堂大学医学部卒業。2012年、順天堂大学附属静岡病院糖尿病・内分泌内科科長(兼准教授)に就任。2016年から日本IBM株式会社にて専属産業医を務めた後、2018年、Basical Health産業医事務所(現Basical Health株式会社)代表に。2021年より、東京国際クリニック 糖尿病代謝内分泌科 非常勤。
糖尿病の2つの種類
糖尿病は、インスリンが十分に働けないために血中のブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気で、大きく分けると1型と2型に分類されます。
1型糖尿病とは?
1型糖尿病は、膵臓のインスリンを作り出す細胞(β細胞)が破壊される病気です。糖尿病全体の約5%が1型糖尿病と言われており、2型糖尿病と異なり生活習慣にかかわらず、比較的小児から若年層で多く発症します。ただし、成人にも発症することがあります。
膵臓でインスリンを作り出すβ細胞が破壊されることにより、インスリンを分泌する力が弱まり、インスリンが不足することで(インスリン分泌不全)高血糖を引き起こすのが、1型糖尿病の特徴です。1型糖尿病は基本的にインスリンが体内で作られなくなるため、インスリン注射が必要になります。このような状態を「インスリン依存状態」と言います。
2型糖尿病とは?
2型糖尿病は、過体重や内臓脂肪の蓄積によりインスリンが分泌しにくくなる(インスリン分泌低下)、インスリンが効きにくくなる(インスリン抵抗性)ことで高血糖を引き起こす病気です。糖尿病患者の95%以上が2型糖尿病と言われており、特に中高年に多く発症します。2型糖尿病は、遺伝的な因子に加え、食べ過ぎや運動不足など生活習慣の影響も大きいと言われています。
糖尿病は遺伝が原因で起きる?

1型糖尿病の原因はまだはっきりしていませんが、遺伝因子やウイルス感染などが誘因となり、自己免疫が関与していると考えられています。約90%が自己免疫性(1A型)、残り10%が特発性(1B型、原因不明)とされています。また、発症しやすい遺伝子として、HLA遺伝子、インスリン遺伝子、CTLA4遺伝子、PTPN22遺伝子などが報告されており、これらの遺伝子を有する患者では家族内発症も認められます。両親ともに1型糖尿病の場合、その子どもが1型糖尿病を発症する割合は3~5%、両親のいずれか一方が1型糖尿病の場合の発症率は1~2%とされています。
2型糖尿病は遺伝的影響があり、両親ともに糖尿病であった場合、40~50%の確率でその子どもも糖尿病を発症すると言われています。ただし、すべてが遺伝によって起こるわけではなく、生活習慣も大きく関係しています。
糖尿病になりやすい生活習慣も「遺伝」する?
2型糖尿病の発症リスクを高める因子は、大きく2つあります。一つは遺伝的因子であり、両親から受け継いだ遺伝子の性質によって、インスリンが分泌しにくい人がいます。もう一つは環境因子で、肥満や食べ過ぎ、運動不足などが糖尿病を引き起こす原因になります。
遺伝ではありませんが、過食や運動不足などの生活習慣が親から子へと受け継がれると、同じ家族内で糖尿病が発症しやすくなる可能性があります。
2型糖尿病になる原因
2型糖尿病の発症には、遺伝的な因子に加えて環境因子も大きく関わっています。環境因子とは、生活習慣や周囲の環境など、遺伝以外の要因を指します。2型糖尿病の発症に関わる主な環境因子は以下のとおりです。
- 不規則な食事
- 運動不足
- 肥満
- 睡眠不足
- 喫煙
- アルコール
- ストレス など
環境因子の一つであるストレスの解消方法やストレスを溜めないためのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。
▼ 関連リンク
経営者によくある3つのストレス 解消方法やストレスを溜めないコツを紹介
2型糖尿病で考えられる合併症
糖尿病で、血糖の濃度(血糖値)が高いまま放置していると血管が傷付いたり詰まったりして、将来、心臓病や失明、腎不全などの重い合併症を引き起こす可能性があります。糖尿病の慢性合併症は大きく「細小血管症」「大血管症」の2つに分類されます。
▼ 細小血管症
- 網膜症
- 腎症
- 神経障害
▼ 大血管症
- 脳梗塞
- 狭心症・心筋梗塞
- 末梢動脈疾患・足病変
また、糖尿病の「3大合併症」と言われるのが、以下の3つの疾患(糖尿病網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病神経障害)です。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症の一つで、目の網膜に起きる障害です。高血糖の状態が長く続くと、目の網膜に広がっている毛細血管が傷付き、進行すると失明するおそれもあります。
眼底検査を受けると、糖尿病網膜症の所見である網膜の出血や白斑、新生血管などがわかるため、早期発見につながります。糖尿病の治療は、内科医の指導のもとで血糖コントロールをおこなうのが基本ですが、定期的に眼科で眼底検査を受け、糖尿病網膜症の早期発見に努めることも重要です。
糖尿病性腎症
糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症による腎疾患で、腎臓の機能が低下する病気です。糖尿病で高血糖の状態が長く続くと、全身の小さな血管が傷んで、血管が詰まります(糖尿病性細小血管症)。特に腎臓は細小血管症が起こりやすく、初期は血液中のタンパク質が尿に漏れ出します。この状態が長く続くと、尿から老廃物を排出する機能が低下します。これが糖尿病性腎症です。
初期の糖尿病性腎症はほとんど自覚症状がありませんが、進行すると、むくみや貧血、高血圧などをともない、さらに進行すると人工透析や腎移植が必要になることもあります。
糖尿病神経障害
糖尿病神経障害は、糖尿病の合併症の一つで神経に起こる障害で、糖尿病の合併症のなかでもっとも多いと言われています。
糖尿病で高血糖の状態が長く続くと、神経(感覚神経、運動神経、自律神経)に障害が及びます。感覚神経に障害が起こると、足先のしびれや痛み、冷感などが起きたり、ものに触れたときの感覚が鈍くなったりします。運動神経に障害が起こると、筋力が低下して歩きにくくなるなどの症状が現れます。自律神経に障害が起きると、立ちくらみや発汗異常、消化不良、下痢や便秘、排尿異常・勃起障害などが起こります。
2型糖尿病の治療方法
2型糖尿病の治療は、生活習慣を改善する食事療法と運動療法が中心になりますが、十分な効果が得られない場合は薬物療法をおこないます。
食事療法
血糖値の上昇を抑え、インスリンの働きを改善するために、「何をどのくらい食べるか」をコントロールします。血糖値を上昇させやすい甘いものや炭水化物は摂取エネルギー全体の50~60%程度に控え、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂り、栄養バランスを考慮することが大切です。
運動療法
運動には血糖値を下げる効果があり、特にウォーキングやジョギング、サイクリングや水泳などの有酸素運動が効果的です。週に5日以上、1回30分程度の運動が推奨されますが、運動の種類や時間は、個人の体力や体調に合わせて調整することが大切です。
薬物療法
食事療法や運動療法だけでは血糖コントロールが難しい場合、薬物療法が追加されます。基本はインスリン注射薬ですが、2型糖尿病の場合には、内服薬から週1回だけの注射薬まで多様な治療薬が存在します。この薬の種類は、糖尿病の種類や重症度などに合わせて医師と相談して決めていきます。もちろん、薬物療法を始めた後も食事療法と運動療法を継続することが大切です。
糖尿病を予防する生活習慣

2型糖尿病は生活習慣病の一つであり、生活習慣を改善することで発症リスクを減らすことができます。生活習慣を改善するとき、特に意識したいのが以下のような点です。
- 食事は腹八分目でやめる
- 食事は1日3食、時間を決める
- 積極的に野菜を摂取する
- 1日30分程度の運動を習慣化する
- 体重を3~5%減らす
- 十分な睡眠をとる
- 禁煙する
- 健康管理のために定期的に健康診断・人間ドックを受ける
- ストレスを溜めすぎないようにする
このような取り組みは、糖尿病の予防だけでなく、脳梗塞や心筋梗塞などの病気のリスクを減らすことにもつながります。
まとめ
糖尿病は、自覚症状がほとんどないまま進行する病気です。体重減少、冷や汗、倦怠感などの症状が現れたときには、すでに血糖値がかなり悪化している可能性があります。放置すると、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすリスクが高まるほか、腎臓や神経、目の血管にもダメージを与え、腎不全や失明につながることもあります。だからこそ、自覚症状がない早い段階で発見し、適切な管理をすることが重要です。毎年の人間ドックを習慣にし、糖尿病のシグナルを見落とさないようにしましょう。
SBIメディックでは、東京駅直結の上質な空間で会員制人間ドックを受けることができ、経営者をはじめとするエグゼクティブの方々に向けた国内最高峰の予防医療サービスをご提供しています。人間ドックを中心とする「予防サポート」はもちろん、専門医のご紹介やセカンドオピニオンなどの「治療サポート」、抗加齢医療や再生医療、エイジングケア、デンタルケアなど加齢に伴い重要になる「エイジマネジメント」までを一体でご提供することで、「いつまでも若々しく健やかな人生」をお送りいただけるようサポートいたします。
▼ 関連リンク
会員制人間ドック「SBIメディック」のプラン・料金などはこちら
※参考:
糖尿病情報センター(国立国際医療研究センター)
e-ヘルスネット(厚生労働省)
一般社団法人 日本糖尿病学会
一般社団法人 日本内分泌学会