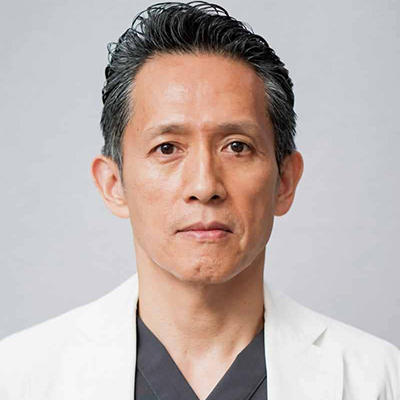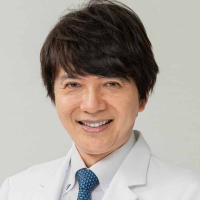Dr.コラム– category –
SBIメディックのドクターがお届けする
お役立ち情報
Dr.'s コラム Dr.'s Column


Dr.'s コラムDr.'s Column
SBIメディックのカウンセリングドクターが書きおこすDr.'sコラムは、病気の知識と前兆を詳しく解説し、みなさまの健康管理と疾病予防をサポートします。専門的な視点から日常生活での注意すべきことや健康診断の重要性について情報を発信していきます。いまを、これからを健康で過ごすために私たちのコラムをお役立てください。
カテゴリー選択Category
カテゴリ選択
最新情報New Topics
-

食いしばり・強い噛みしめを治療する ~咬筋へのボトックス注射~
頭痛や肩こり、無意識の噛みしめが原因? -

歯周病治療と精密保存治療、2つの柱で口腔内の健康を守ります。
「歯を残す」ための最新歯周病・むし歯治療 -

生活の質が大きく低下する「帯状疱疹」は予防できる疾患です。
50歳からのワクチン接種で激痛予防 -

遺伝子検査とAI(人工知能)画像診断
採血とAI診断でがんの早期発見へ -

肩こりや腰痛に効果があるプラセンタ注射(トリガー注射)
痛みの引き金(トリガー)に直接アプローチ -

夏もきちんと発汗を。多汗症の最新治療
汗の悩み、原因は?ボトックス治療も紹介 -

不整脈が脳梗塞を招く!? ~心原性脳塞栓症~
検診で早期発見!心房細動が作る血栓 -

歯の長期的な健康のために -歯の神経を残すことの重要性-
神経を抜くと歯は“枯れ木”に -

肌再生プレミアムピール(コラーゲンピール)をご存知ですか。
肌深層を刺激し、ハリ・透明感を改善 -

リラックスして歯科治療を受けていただくために
歯科恐怖症の方へ。「静脈内鎮静法」とは -

膵臓がん、胆のう・胆管がんの検査「MRCP(MR胆管膵管撮影)」とは
増加する膵臓がん等の早期発見に -

シミとしわについて
肌老化の2大原因「紫外線」と「乾燥」対策 -

エイジマネジメントのための検査
糖化・ストレス・ミネラルを検査 -

マイクロスコープを使った精密な歯科治療をご存知ですか?
歯を残すための「見える」精密治療 -

心不全とWPW症候群
進行する心不全と、突然死リスクの不整脈